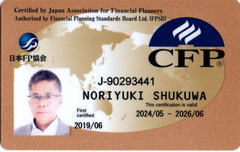相続相続債権が回収できない債権が回収できない

相続が発生し、遺言が無い場合には法定相続人全員で遺産の分け方を話し合い「遺産分割協議書」を作成します。これには、法定相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議の対象となる遺産は「プラスの財産」です。借金など「マイナスの財産」は対象外です。債権者保護のために、マイナス財産は法定相続分で相続することになります。債権者が承諾すれば、相続人の一人が債務を引き受けることはできます。
被相続人がお金を貸していた場合、プラスの財産(債権)となりますので、遺産分割協議で相続人の誰かが取得することとなりますが、債務者が返済できない場合はどうなるのでしょうか?
【遺産分割協議】
遺産分割協議とは、遺産を法定相続人の話し合いで分割することを言います。
遺産には、いろいろなものが含まれます。
・預貯金
・不動産
・動産(自動車、高級時計、ゴールド、絵画、宝石...)
・金融資産(ゴルフ会員権、上場株式、投資信託...)
・貸付金等の債権
預貯金も債権の一種ですが、金融機関が存在する限りほぼ確実に回収できます。
一番最後に記載した貸付金等については、例えば相手が自己破産などした場合には回収できなくなってしまいます。
遺産分割協議のときには、100万円の預金と100万円の貸付金は同じ価値の遺産として分割していますが、回収できない場合、貸付金を取得した相続人だけが損害を受けてしまいます。
かと言って、貸付金を現金化してから遺産分割するとなると、貸付金の返済期まで遺産分割ができなくなってしまいます。
【共同相続人の担保責任】
遺産分割によって分けられた遺産について問題がある場合
・遺産と思っていたが、他人の財産だった
・数が少なかった、一部無くなっていた
・遺産に制限が付いていた(要益権、担保権など)
・隠れた不具合があった
・債務者が無資力(借金を返してもらえない)
このような場合、法律で、
「各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売り主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。」
と定められています。貸付金が回収できなくなったときには、他の遺産(預貯金や不動産など)を取得した相続人がその分を補填しなければなりません。
条文中の相続分は法定相続分ではなく、遺産分割協議により決めた相続分のことです。実際に多く遺産を取得した人が、その分多く負担することにより、相続人の衡平を図ろうという考え方です。
遺産分割の際、返済期限が来ていない債権があった場合には、後でその分の負担が発生する可能性がありますので、頭に入れておいてください。